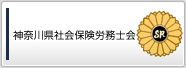トップページ > 新着情報
被用者保険の企業規模要件「撤廃」多数 (2024年6月17日)
被用者保険の適用範囲に関する議論を進めている厚労省の有識者懇談会にて、11日、今年10月から従業員51人以上に拡大される企業規模要件と、非適用業種の撤廃を求める声が多く挙がった。撤廃された場合、適用対象が約130万人増える見込みで、事業主への支援や準備期間確保の必要性も指摘された。マルチワーカーやフリーランスへの適用拡大は実務負担が大きいとして、意見が分かれた。議論は来月にも取りまとめられる予定。
個人情報漏洩件数 初の1万人超 (2024年6月17日)
個人情報保護委員会は11日、2023年度に企業や行政機関等から報告された個人情報漏洩件数が、17年度以降で過去最多の1万3,279件となったと発表した。1万件超は初。22年度以降、個人情報漏洩の際の委員会への報告や本人への通知が義務化されたことなどで報告件数が急増している。
4月の有効求人倍率は1.26倍 (2024年6月10日)
厚生労働省の5月31日の発表によると、4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍(前月比0.02ポイント減)となった。物価高による収益悪化から、求人を控える傾向が続いている。製造業の新規求人数が減少(前月比7.8%減)し、4月から残業時間の上限規制が適用開始となった建設業(同3.9%)や運輸・郵便業(同2.3%)などでも減少した。一方、総務省が発表した同月の完全失業率(季節調整値)は2.6倍と、2カ月続けての横ばいとなった。
老齢年金請求手続の電子申請が可能に (2024年6月10日)
厚生労働省は、3日から単身者で他の公的年金を受け取っていない人の老齢年金について電子申請で請求手続がきるようにした。事前準備ができている場合、スマートフォンなどで「マイナポータル」にアクセスすると、15分程度で申請が完了するという。3日より電子申請が可能なのは24年度に65歳を迎える人の1割程度程度にとどまり、今後は配偶者がいる人も対象とするため、対応を急ぐ。
改正子ども・子育て支援法が成立 (2024年6月10日)
少子化対策を盛り込んだ改正子ども・子育て支援法が5日、参院本会議で賛成多数により、成立した。児童手当の所得制限撤廃、高校卒業までの支給期間延長は、令和6年12月に支給される10月分から実施。児童扶養手当の第3子以降の加算額引上げは令和7年1月に支給される令和6年11月分から実施される。また「共働き・共育て」の推進に向け、出生後休業支援給付および育児時短就業給付が創設される。財源の1つとして創設される支援金は、令和8年度から医療保険料とあわせて徴収される。
改正育児・介護休業法が公布 (2024年6月3日)
31日、改正育児・介護休業法が公布された。これまで支援の中心は「3歳に満たない」子を養育する労働者だったが、「小学校就学の始期に達するまで」に拡充され、子を育てながら柔軟に働けるような制度の導入が企業に義務付けられる。さらに、男性の育児休業取得率の公表を求められる企業が1,000人超から300人超へと拡大される。
厚生年金 企業規模要件を撤廃へ (2024年6月3日)
厚生労働省は、短時間労働者の厚生年金加入をめぐる企業規模要件について、撤廃する方針を固めた。試算によると、新たに130万人が適用対象者に加わる。また、従業員5人以上の個人事業所の非適用業種も原則撤廃し、飲食業や宿泊業なども対象とする見通し。6月にまとめる骨太の方針に盛り込考え。
60歳以上の労災3.9万人、8年連続の増加に (2024年6月3日)
厚生労働省の27日の発表によると、昨年に労働災害で死傷した60歳以上の人は、前年比1,714人増の3万9,702人(うち死者290人)で、8年連続過去最多となった。労働者全体(死傷者数13万5,371人)に占める60歳以上の割合は29.3%。足がもつれたり、つまずいたりしたことによる転倒や、階段からの転落が多いとみられる。
企業の28%で従業員からカスハラ相談
(2024年5月27日)
17日に公表された厚生労働省の調査結果(「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」)で、過去3年間で従業員からカスタマーハラスメントについて相談を受けたと回答した企業が約28%に上ることが、わかった。また就職活動やインターンシップを経験した男女への調査では、約3割がセクハラ被害に遭ったと回答したことも、明らかとなった。
フリーランス新法 11月1日施行
(2024年5月27日)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、11月1日に施行されることとなった。20日の厚生労働省の検討会では就業環境の整備に関する具体的な内容を定めるための報告書がまとめられ、発注者に出産・育児や介護との両立への配慮を義務付ける業務委託期間を「6カ月以上」とすることが決まった。同日公表された報告書をもとに、政省令の公布の準備を進める。