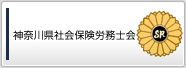トップページ > 新着情報
障害年金 未納者向け特例措置延長へ (2024年8月26日)
厚労省は、1985年から導入されている障害年金の特例措置について、10年間の延長を2025年の年金制度改革に盛り込むする方針を固めた。同措置は、障害の原因となった病気等に係る初診の月の前々月までの1年間で年金保険料の未納がなければ、過去に長期滞納があった場合でも受給できるというもので、現行の期限は2026年3月末までとなっている。
教員の処遇改善 来年度予算概算要求に関連経費 (2024年8月26日)
文科省は21日、公立学校教員の処遇改善案を示した。教員の「残業代」に該当する「教職調整額」を引き上げる方針で、2025年度予算の概算要求に関連経費を盛り込み、来年通常国会に関連法案を提出する方針。あわせて私立学校を運営する学校法人への補助金を増額する方針で、2025年度予算の概算要求において、今年度予算額から3%増の868億円(2012年度以降最大の上げ幅)を盛り込む。
決済大手PayPay、賃金デジタル払い初事業者に 厚労省が認可 (2024年8月19日)
厚生労働省は9日、スマートフォン決済サービスのPayPayを「デジタル給与払い」に対応する最初の事業者として指定した。2024年内には、全ユーザーを対象に、給与をデジタルで受け取れるサービスを開始する予定。この制度の利用拡大により、労働者の利便性向上や、企業の事務作業の効率化が期待されている。
ギグワーカーの働き方改革 賃金や有給休暇の基準を明確化 (2024年8月19日)
厚生労働省は、ギグワーカーの待遇改善に向け、新たな指針を策定する。これにより、ギグワーカーにも最低賃金の適用や有給休暇の取得が可能となり、労働条件の透明化が進む。従来の労働法の枠組みを超え、多様な働き方に対応できる柔軟な労働環境を整備する。人手不足に悩む企業にとっても、ギグワーカーとの契約が円滑に行えるよう、制度の整備を進める。
宿直中の休憩を労働時間と判断 未払い額最大86億円 (2024年8月19日)
8日、東京メトロを運営する東京地下鉄は、24時間拘束される全泊勤務の社員の休憩時間が労働時間に当たるとして割増賃金を支払うよう2日付けで是正勧告を受けた、と発表した。対象者は約1,800人、未払い分として3年間で最大で86億円を支払う見通し。同社では全泊勤務中に全員が同じ時間帯に休憩を取っており、実際に緊急対応を行った社員に代わりの休憩時間を設けたり残業手当を支払ったりしていたが、管轄の足立労働基準監督署は、社員からの申告で1月頃から調査の上「労働から完全に解放されておらず労働時間に該当する」と判断した。
国家資格の登録等手続をオンライン化 (2024年8月16日)
デジタル庁は2日、国家資格の登録・変更等の手続きをオンライン化することを発表した。まずは社会福祉士、介護福祉士などの4資格で6日からスタートし、今後、約80の国家資格のデジタル化を進める。マイナンバー制度を活用することによるもので、登録や変更の手続き以外に、手数料のオンライン決済や保有する資格を電子的に示すデジタル資格者証の発行なども始める。
実質賃金 27カ月ぶりのプラス (2024年8月16日)
厚生労働省が6日に6月の毎月勤労統計調査(速報)を発表し、実質賃金が前年同月より1.1%増と27カ月ぶりのプラスとなった。現金給与総額のうち、所定内給与は2.3%増となった一方、賞与を含む「特別に支払われた給与」は7.6%増となったため、賞与を6月に支払った企業が多いことがプラス転換の主な要因で、増加は一時的との見方もある。
後期高齢者医療の現役世代負担 2年連続で過去最大 (2024年8月16日)
8日、厚生労働省は後期高齢者医療制度の2022年度の財政状況を公表した。全体の支出は前年度から3%増加し17兆724億円と過去最大となった。このうち、保険給付費は4%増の16兆4,749億円。全体の収入は2%増の17兆4,629億円で、このうち現役世代が支払う交付金は前年度から3%増の6兆6,989億円と、2年連続で過去最大を更新した。
6月の求人倍率と完全失業率 (2024年8月5日)
厚生労働省の30日の発表によると、6月の有効求人倍率(季節調整値)が1.23倍(前月比0.01ポイント減)と3カ月連続で低下した。27カ月ぶりの低水準。物価上昇により高い収入を得られる企業への転職が増える一方、コスト上昇により企業が求人を手控えている状況がある。一方、総務省が同日発表した同月の完全失業率は2.5%(同0.1ポイント減)だった。
22年度の社会保険給付費 初の減少 (2024年8月5日)
国立社会保障・人口問題研究所は30日、2022年度の社会保険給付費が137兆8,337億円で、集計開始以来初めて減少したことを発表した。過去最高だった前年度より9,189億円(0.7%)減。新型コロナウイルス感染症関連の費用が減少したためで、内訳は、「福祉その他」が33兆2,918億円(前年比6.3%減)、「年金」は55兆7,908億円(同0.04%減)、「医療」は48兆7,511億円(同2.8%増)だった。